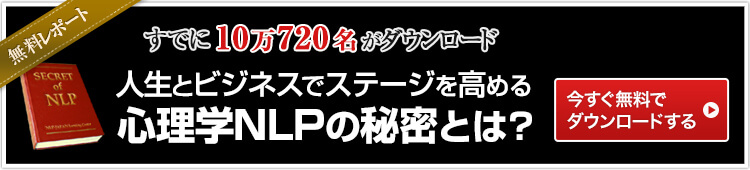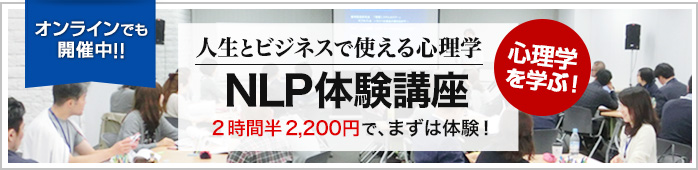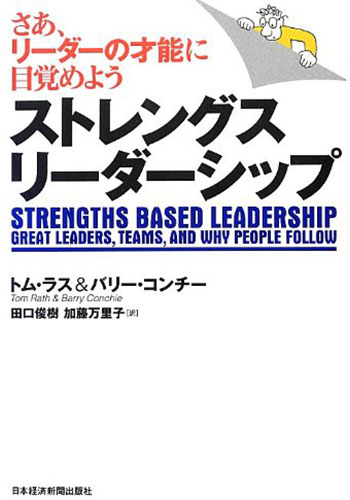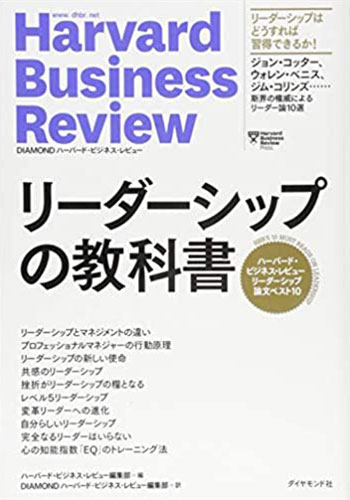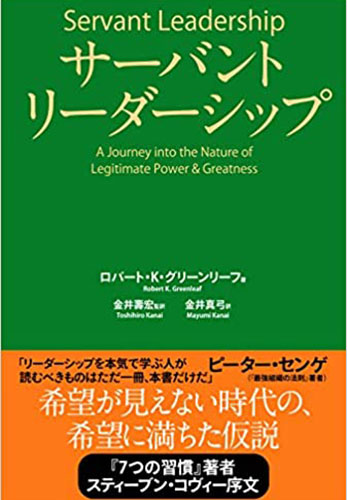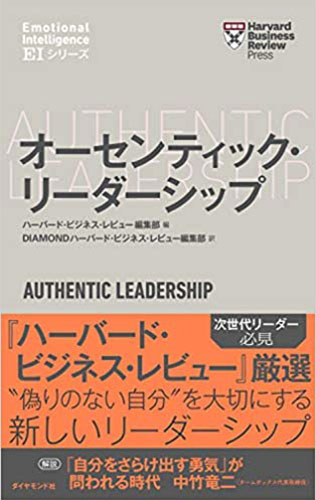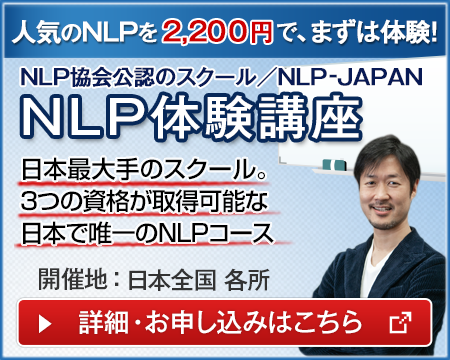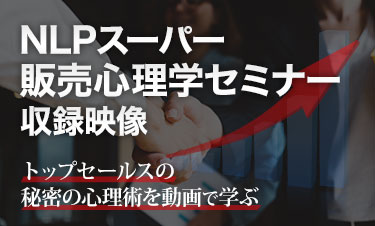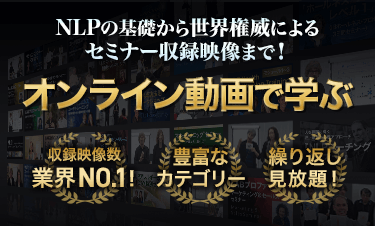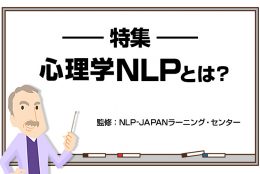- 「優れたリーダーシップって何だろう?」
- 「具体的なやり方は?」
- 「リーダーシップのポイントって?」
このような疑問を持ち、
リーダーシップを取るための秘訣を知りたい
と思っていらっしゃる方も多いかもしれません。
そこで、この記事では、
ビジネスでの成果や年収を高め、
やりがいを生む、リーダーシップの高め方や
身につけ方についてご紹介していきます。
1.リーダーシップとは?

リーダーシップとは、チームや組織をゴールの達成のために統率する能力のことをいいます。
例えば、課題や困難に直面した際に、チームのモチベーションを高めることや、状況の変化に素早く対応する力のことです。
リーダーシップを身につけることができれば、組織の団結力を高め、目的の達成に導くことができるのです。
1-1.リーダーシップとリーダーの違い
リーダーシップについてお伝えする上で、よく耳にするリーダーとの違いを明確にすることで理解が更に深まるのではないでしょうか。
リーダーシップとは、チームや組織の課題や困難に対して、みずからチームに貢献する『能力』のことです。リーダーシップを発揮することで、チームメンバーとともに課題や困難をクリアしていくことができます。
その一方で、リーダーとは、基本的には『役割』の事です。
そして、「成果に責任を負うこと」が求められます。
チームや組織が向かう方向性を決め、その方向性からずれてしまいそうなときに旗を振り、方向を修正し導いていくことです。
また部下や周りの人から支持され、認められることも大事です。
「この人の影響を受けたい、ついていきたい」と思われることで、協力を得て、大きな成果を出すことができるのです。
1-2.リーダーシップとマネジメントの違いについて
リーダーシップは、チームを率いる能力です。また、目的を達成させるために組織を導くことです。
それに対して、マネジメントとは、目標・ゴールを達成するための「計画やプロセスを管理すること」です。
例えば、より効率的に、スピーディーに達成するためにどうすればいいかを考えたり、計画が遅れたりしてしまった際に、目標・ゴールを達成するために、再度計画を設定することです。
以上をまとめると、「リーダーシップとは、行き先を示し」「マネジメントとは、そのプロセスを管理すること」です。
1-3.リーダーシップの種類
最近では、リーダーシップの種類の幅は大きく広がっています。
例えば、PM理論や、ビジョン型リーダーシップ、コーチ型リーダーシップのEQ理論や多種多様なリーダーシップの形が提唱されています。
また、それぞれの種類によって強みも変わってきます。
自分はどのようなリーダーシップの形が理想なのかを知ることは非常に重要です。
なぜなら、理想像に向かった経験値を積み重ねることができるからです
そのためリーダーシップの種類について知ることもおすすめです。
リーダーシップの種類について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
2.リーダーシップに必要な要素7選
リーダーシップとは、組織を率いるために必要な能力のことをいいます。
ここからは、リーダーシップに必要な要素を7つご紹介していきます。
ぜひ、あなた自身にどんなことが活かせるかを考えながら、読んでみてください。
2-1.コミュニケーション能力
コミュニケーション能力は、リーダーシップには欠かせない要素の1つになります。
コミュニケーション能力が高いことで、その人に適した言葉がけや、相手の立場に立った会話をすることが可能になるからです。
その一方で、コミュニケーション能力が低いと、どんなにリーダーシップを磨いたとしても、周囲を率いることは難しいでしょう。
なぜなら、相手に伝えたいことを正しく伝えることや、相手の気持ちを察した会話をすることができないことにより、組織のメンバーとの信頼関係の構築をすることができないからです。
また、どんなに熱心に話をしても、相手が素直に受け入れることができず、周囲の協力を得ることも難しくなってしまいます。
そのため、チームのモチベーションを上げるコミュニケーションや、相手の立場に立ち、相手と信頼関係を築くためのコミュニケーション能力が非常に重要なのです。
2-2.ビジョンを描く能力
ビジョンとは、組織やチームの可能性や方向性のことです。
ビジョンが明確になることで、メンバーのモチベーションをあげることにもつながります。
- 組織やチームが、どのような成長を遂げていくのか
- どのように人、社会に貢献できるのか
- どのような世界をつくり上げることができるのか
これらのビジョンを思い描くことができれば、メンバーのやりがいに繋がります。
特に、困難な状況においてビジョンを示し、希望を見出すことは、メンバーの不安を打ち消し、未来への期待に変えることができるのです。
ビジョンを描くことができれば、具体的な方向性を、チームに示すことができるようになります。
反対に、ビジョンを描くことができなければ、組織のメンバーが仕事の大義を見失い、なんのために仕事をしているのかわからないまま、目の前の業務をこなすだけになってしまいます。
これにより、モチベーションの低下につながります。
そのため、リーダーシップには、方向性を示し、目的を明確にするためのビジョンを描く能力が必要なのです。
2-3.安定感
安定感は、チームを率いる中で非常に重要です。
特にリーダーのモチベーションの安定は組織では欠かせない要素になります。
なぜなら、リーダーのモチベーションの安定が組織に大きな影響を及ぼすからです。
例えば、日によって機嫌や態度が異なるリーダーのもとにいるメンバーは、リーダーに声をかけるタイミングや顔色を伺いながら、日々仕事をすることになります。
このような状況が続けば、仕事のスピードが低下し、モチベーションの低下につながることは容易に想像できるでしょう。
誰にでも、イライラするような出来事や、決断の連続の中で不安になることもあります。
ただし、組織を率いるリーダーとしては、安定感は非常に大切になってくるのです。
2-4.洞察力
洞察力とは「物事の本質を見る力」です。
リーダーシップにおいて、洞察力はとても重要な要素です。
理由として、仕事の本質や目的を見失った組織は、ただ目の前の数字に追われ、疲弊してしまう可能性が高いからです。
例えば、営業のノルマや、日々行っている簡単な業務など、ただこなしているだけでは、いずれモチベーションの低下に繋がります。
そんな状況が続けば、なんのために仕事をしているのかわからなくなり、仕事がストレスになってしまうなどマイナスな影響を与えるでしょう。
その中で「仕事の目的」や「やりがい」などの本質を見抜き、大切な部分を外すことなく、組織を牽引することができれば、大きな成果にも繋がります。
そのため物事の本質を見る、洞察力はとても重要なのです。
2-5.人間性
リーダーシップにおいて人間性は、非常に大切です。
人間性がなければ、どんなに決断力や洞察力などの要素があったとしても、組織を率いることは難しいです。
特に、人間性の中でも「組織の手本になること」はとても重要です。
例えば、組織を率いる立場であるにも関わらず、部下に横柄な態度を取る人や、人によって大きく態度を変える人に従いたいとは誰も思わないでしょう。
また、仕事で成果をだすために、誰よりも努力する姿も重要です。
なぜなら、組織で結果を出すための努力をする姿も、組織の手本となるからです。
例えば、自分よりも成果を出していない上司に、指摘をされたとしても、素直に指摘を受け入れることはできるでしょうか?
多くの人は「NO」と答えるでしょう。
加えて、努力もせずに結果を出した人は、できない人の気持ちを理解することもできず、その人に合ったアドバイスをすることもできません。
そのため、態度や普段の姿勢も大切ですが、仕事で成果を出すために努力をすることも、組織の手本となるためには必要なのです。
このような人間性を磨くことができれば、自ずとリーダーシップが身につきます。
そして後から、役職や地位が自ずとついてくるでしょう。
2-6.リスク管理能力
チームを率いていくなかで、トラブルはつきものです。
リーダーシップには、ミスやトラブルを未然に防ぐ、リスク管理能力が必要です。
なぜなら、リーダーは責任を負う立場になるからです。
部下のミスだとしても、最終的な責任は、リーダーにあります。
事前にミスを防ぐような声がけや対策を行うことができていれば、結果は大きく変わってきます。
そのため、まずは業務をする中で、どのようなリスクがあるのかを考える、リスク管理能力がリーダーシップの要素の1つになるのです。
2-7.決断力
リーダーシップにおいて、決断力は非常に重要な要素です。
組織を率いる中で、何か決断をせまられることは、必ずあるといっても良いでしょう。
あなたの決断で組織の命運が分かれることもあるかもしれません。
そのため、決断力はリーダーシップで必ず必要な要素になります。
- 組織の方向性をどのようにしていくのか
- トラブルにどのように対応するのか
- 人員の配置はどうするのか
このような決断をしなければいけないとき、あなたならどうしますか。
決断力がなければ、好機を逃すこともあれば、組織をマイナスな方向に進めてしまう可能性があります。
決断をしなければいけない時がいつ来るかは、わかりません。
そのため決断の機会に備えた、決断力が非常に重要になります。
3.リーダーシップを身につける方法5選
この章では、みなさんの中にあるリーダーシップを引き出し、身につける方法を紹介していきます。
3-1.リーダーシップがある人を真似る
ここでご紹介する1つの方法は、身近にいる身近にいるリーダーシップが優れていると思う方をよく観察し、マネをするというものです。
このようなやり方を心理学NLPでは特にモデリングと呼びます。
身近な人、尊敬する人、歴史上のリーダーシップのある人物だったらどのように考え、振舞うか。繰り返し繰り返し、あたかも自分自身がその人のように行動をすることを意識してみてください。
これらを積み重ねることで、リーダーシップがある人のような行動をとることができるようになります。
※モデリングに関して詳しくはこちらをご覧ください。
3-2.共感を意識する
共感とは、相手の価値観や感情に寄り添い、受け止めることです。
共感をすることにより、相手があなたの意見を受け入れやすくなり、より円滑にチームを率いることが可能になります。
また、チーム内での信頼関係の構築にも繋がります。
共感をするための具体的な方法として、「バックトラッキング」というスキルが非常に効果的です。
バックトラッキングとは、相手の言葉をそのまま繰り返すことです。
バックトラッキングには以下の2つの方法をご紹介します。
- 事実
- 感情
- 要約
例えば、
【事実のバックトラッキング】
部下:「最近、仕事でミスが多くて」
あなた:「最近、仕事でミスが多いのか」
【感情のバックトラッキング】
部下:「そうなんです。それがかなりつらくて。。。」
あなた:「かなりつらいのか。大変だね。」
このように、部下から言われたことに対して、事実や感情などの言葉をそのまま繰り返します。
このようなことで良いのか?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
安心してください。
バックトラッキングは、相手が話を理解してもらっているという気持ちや、受け入れてもらっているという印象を与えることができます。
そのため、まずは共感をすることを意識してみてください。
バックトラッキングについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。
3-3.コミュニケーション能力を鍛える
コミュニケーション能力を鍛えるために、相手の立場に立つトレーニングをすることが効果的です。
なぜなら、人によって動機づけされる言葉や、響く言葉は異なるため、相手の立場に立って、その人に合った言葉を使えるようになることが大切だからです。
自分が聞いてモチベーションが上がる言葉でも、他の人も同様にモチベーションが上がっているとは限りません。
そのため日々、相手が使っている言葉を観察することや、相手の立場に立つということを意識してみてください。
そして、その人に合った言葉がけをすることで、あなたのリーダーシップの発揮につながるでしょう。
人を動かす言葉についてさらに知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
3-4.まずは行動する

組織やチームで決定したことはもちろん、どの方法が有効かわからない時にまずはやってみる、実行するということは何においても重要です。
成果を出している人は「計画6割」とよく言われ、とにかく決断し、実行することでチャンスを生み出しています。
躊躇していたり、完璧な準備をしたりしていたら、他人や他社がそのチャンスを自分のものにしてしまいます。どんなに立派な目標やゴールであっても、実行することが出来なければ絵にかいた餅で終わってしまいます。
そして、困難なときや、人が躊躇してしまうときほど、率先してやることが後々、大きな差となっていくのです。
そもそも躊躇や、完璧な準備をしてしまう背景には「失敗したくない」という気持ちが大きくあることが大半です。
ですが、大きな成果を出している人は、沢山の失敗を経験しています。むしろ、失敗していない人が大きな成功を手に入れることはないのです。
そこで、自身の過去を振り返ったとき、あまり挑戦してこなかったと感じたり、結果他の人に成果を明け渡してしまったという方ほど、6割の準備ができたら実行することをお勧めいたします。
3-5.新しいことに挑戦する
リーダーシップを鍛えるために、新しいことに挑戦をして、経験値を増やすことが非常に有効です。
なぜなら、多くの経験を積むことによって、知識の幅が増え、完成を磨くことができるからです。
例えば、何かミスをした時、初めてのミスであれば、どのように対処すれば良いのかわからないこともあるでしょう。
しかし、経験値があれば、今までの経験から、対処法を思いついたり、似たできごとから対策を考えることもできます。
また、コミュニケーションにおいても、人生の経験値によって、相手のモチベーションを上げる際の言葉の重みが出てきます。
そのため、経験値を増やすことはとても重要なのです。
経験値を増やすためには、多くのことに挑戦することや、今までやってこなかったこと、読書をすることなどがオススメです。
あなたの人生の幅を広げ、優れたリーダーシップを手に入れてみてください。
4.あなただけのリーダーシップを探す

3章では、身に着ける必要のある、リーダーシップについて見てきました。
この章では、さらに、自分ならではのリーダーシップを見出し、発揮していく事で、もっとも無理なく、影響力を最大にしていく事について見ていきます。
「自分ならではのリーダーシップ」に気づき、それを発揮することは非常に重要です。
「自分ならでは」とは、自分の中にある自分にしかない要素に気づき、発揮することです。
自身の能力を最大限引き出すこととなり、以下のようなリーダーシップを発揮できるようになります。
- 仕事に喜びを感じ
- 周囲とのコミュニケーションも円滑になり
- チーム全体の目標達成にもつながる
さらには仕事だけでなく、自分の人生を豊かに生きることにまでつながるのです。
現在にいたるまで、「最高のリーダーシップとは何か」という研究が多くなされてきました。その中で現在言われていることはこちらです。
「模範となる唯一の最高のリーダーシップは存在しない」
つまりそれは、人のリーダーシップをそのまま全てをまねることではなく、自分ならではのリーダーシップを見出し、発揮することに他なりません。
目の前にいる尊敬できる先輩や、有名な起業家、歴史上の人物のようになりたいと思うことそのものは、決して悪いことではありません。
ですが、すべてにおいてその人のようになろうとすると、その人自身ではないのでどこかしら無理が出てきてしまうことになるのです。そして、人との関わりや、自身の健康に望ましくない結果として現れたりするのです。
5.リーダーシップお勧め本
この記事の最後として、リーダーシップ書籍をご紹介していきます。今の時代に求められるリーダーシップをさらに知りたいという方へ、お勧めの4冊になります。
5-1.さあ、リーダーの才能に目覚めよう ストレングスリーダーシップ
「あなたならではのリーダーシップを見出そう」
40年も前から現在まで世界中で読まれ、自分の強みをWEB上で診断・把握できる、「ストレングスファインダー」の続編。
自己の強みをすぐに知りたい、強みをリーダーシップに活かしたいという方にお勧めの1冊です。
このストレングスリーダーシップでは、自身のリーダーシップ要素を見出し、書籍に書かれた、優れたチームに共通する4つの条件と照らし合わせ、どのようなリーダーシップの発揮の仕方が効果的かアドバイスも得ることができます。
5-2.ハーバードビジネスレビュー リーダーシップの教科書
「リーダーシップについて、第一線の研究者が書いた論文集」
リーダーシップの基本的な考え方から、リーダーがさらにレベルアップするための方法までが書かれた1冊。
リーダーシップの基本的考え方、身に付け方、磨き方。リーダーのタイプがどのように組織で機能しているのかを知りたい方にお勧めです。
リーダーシップについて知っておくべき最低限のこととして厳選した10本の論文を集めたもので、1つ1つが深い内容にもかかわらず、読みやすくなっています。
また、各書籍の興味深い1節を集約しているので、興味を持った1節の書籍へ読み進めることができ、更なる知識を得ることができます。
5-3.引っ張るリーダーから支えるリーダーへ サーバメントリーダーシップ入門
「ミッションに向かって自発的に歩み始める人を後押しする」
近年注目されている、コンセプト論のサーバメントリーダーシップについての書籍で、サーバメントリーダーシップについて詳しく学びたい方の入門書として最適です。
日本での事例が多く、著者の実体験からわかりやすく解説されており、身近に感じられ、サーバメント(奉仕型)を具体的にどのように組織に入れていくかがわかる1冊。
5-4.ハーバードビジネスレビュー オーセンティック・リーダーシップ
「自分らしいリーダーシップとは?その本質とメリット・デメリットを説く」
カリスマを真似るのではなく、自分なりの価値観をもとにしたリーダーシップについて書かれた書籍です。
オーセンティック・リーダーシップとは、一言で表すと自分らしさを持つこと。自分らしさとは何かを知りたい方にお勧めです。
自分らしさとは何かを、テーマごとに端的に説明しており読みやすい1冊です。また、自分らしいリーダーシップのメリット、そして陥りやすい問題、回避したいデメリットについても解説されています。
6.まとめ
リーダーシップとは、チームや組織のゴールを達成するため、その時々のチームの課題や困難を乗り越えるために、誰もが持っている考えや能力のことでした。
そして、自分の内面にあるリーダーシップを探求し、見つけ、発揮することで、仕事の成功や目標達成、周囲に影響を与える人になることができるのです。
リーダーシップを発揮するために、ここで紹介した方法を実践し、自分ならでのリーダーシップを見つけていきましょう。