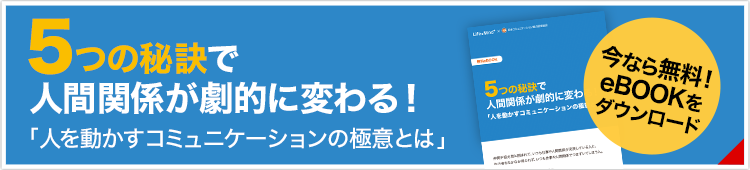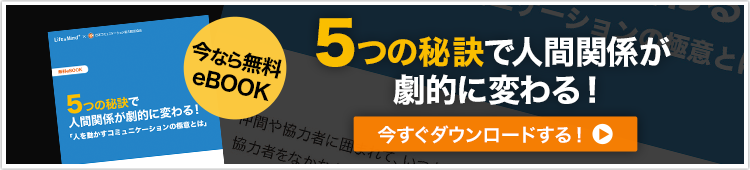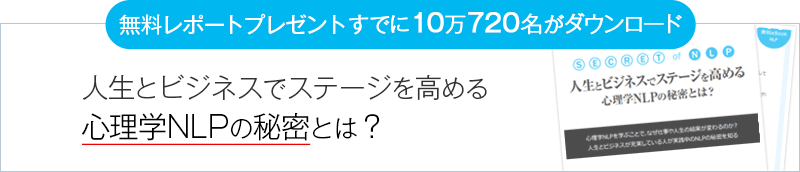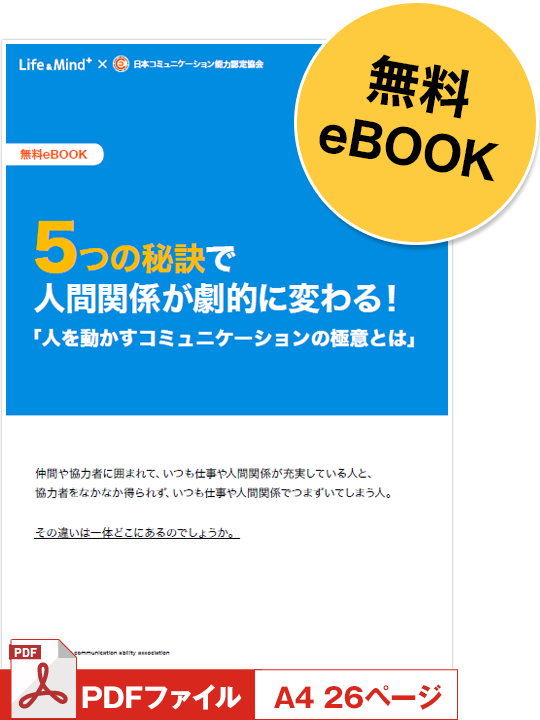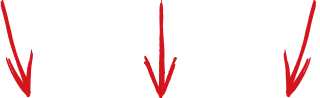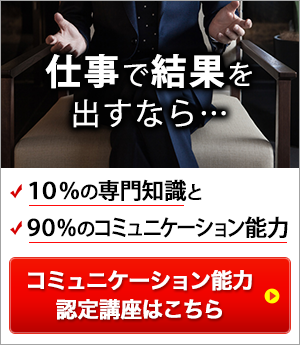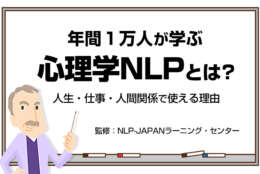「社内で情報共有ができていない」
「大事な報告がすぐに上がってこない」
組織で働く人にとって、一度は頭をよぎる状況かもしれません。
社員同士の対話を大切にして、意見を言いやすい、風通しのよい環境づくりをする。
これらは、社内コミュニケーション活性化を考えるうえで、誰もが十分に承知していることでしょう。うまくいかない状況が実在するのは、具体的な取り組みに焦点を当てる必要があるからなのです。
では、実際にどのような取り組みをし、どのように進めていけばよいのか、
ここでは具体的な事例と、その効果を含めご紹介していきます。
| 監修:日本コミュニケーション能力認定協会 | |
コミュニケーションの専門機関として “満足度99.3%” の『コミュニケーション能力認定講座』を開催。日本教育推進財団が監修し、19万人の指導実績に基づくコミュニケーション・カリキュラムは、信頼の獲得・リーダーシップの発揮・営業や交渉での成功・人間関係の構築に効果的。メディアからも注目されている。 | |
目次
1.社内コミュニケーション活性化がもたらす3つのメリット
そもそも、社内コミュニケーションが活性化すると、どんなメリットがあるでしょうか?
社内コミュニケーションが活性化すると、3つの循環がうまく回るようになります。
- 生産性が上がり、業績が向上する
- 仕事のやる気が増す
- 職場への満足度が上がる
社内コミュニケーションとは、人と人はもちろん、人と組織、組織と組織の情報共有をスムーズにするということに他なりません。
情報共有が円滑に行われれば、情報の漏れや時間のロスが減り、生産性が上がります。生産性が上がることで、業績が向上し、仕事のやる気が増していきます。そして、仕事のやる気は職場への満足度にもつながっていくのです。
では、どうやって情報を共有すればよいのか。次章では、情報共有に便利なツールと仕組みを、具体的な事例と効果とともにご紹介していきます。
2.社内活性化事例5選と効果
2-1.チャットワーク活用事例と効果 (経営コンサルタント神田昌典氏)
2-1-1.チャットワークとは
インターネット上で利用できるチャット(会話)ツールです。利用登録した後はインターネット回線がある場所からであればどこからでも利用でき、個別でチャットする場合でも、複数人数でのグループチャットも可能なため、今多くのビジネスシーンで活用されています。
※チャットワーク(ChatWork)⇒ http://www.chatwork.com/ja/
2-1-2.経営コンサルタント神田昌典氏のチャットワーク活用事例
・導入前の課題と目的
2010年当時、神田昌典氏は、コミュニケーションツールとして使用していた電子メールに課題を抱えていました。縦割り組織の弊害で、事業部を越えた横のコミュニケーションがうまく取れず、プロジェクトが進まないという状況に直面していたのです。そこで、よりプロジェクトベースで仕事をすることができないかと考え、チャットワークを導入しました。
・導入後の効果
グループチャット機能を用いて、プロジェクト毎にグループを作成。プロジェクトに関わる人とダイレクトにコミュニケーションが取れるため、事業部を越えた横のコミュニケーションが円滑になりました。
<電子メールのデメリット>
プロジェクトをイメージするのが難しく、各プロジェクトがどのように動いているのか図式化するのが難しい。
<チャットワークのメリット>
パッと見て、プロジェクトがどう動いているのか、ひと目で分かるようになりました。どれだけのプロジェクトが動いているのか、そして動いているものと動いていないものの区別ができるようになったのです。
またチャットワークを活用することで、事業部を越えた横のコミュニケーションが円滑になる、という効果がありました。
2-1-3.チャットワークはこんな人、組織にオススメ
チャットワークは、こんな悩みを抱えている人や組織にオススメです。
- 組織や部署を越えた横のコミュニケーションを円滑にしたい人や組織。
- プロジェクトがなかなか進まないと悩んでいる人や組織。
- チームで仕事をしているあらゆる人や組織。
チャットワークは、枠を越えた横のコミュニケーションを円滑にします。これらの悩みを抱えている方は活用してみてはいかがでしょうか。
2-2.フリーアドレス制度の活用事例と効果(日本マイクロソフト株式会社)
2-2-1.フリーアドレス制度とは
フリーアドレス制度とは、職場で社員一人ひとりに固定した席を割り当てず、在社している社員が仕事の状況に応じて空いている席やオープンスペースを自由に使うオフィス形態です。あるいは、そうした制度を活用して柔軟かつ効率的に業務を進めるワークスタイルをいいます。
2-2-2.日本マイクロソフト株式会社のフリーアドレス制度活用事例
・導入前の課題と目的
2011年、本社を品川へ移転するにあたり、旧本社では部署ごとに各人のデスクがパーテーションで囲まれており、コミュニケーションの範囲が非常に近いグループ内に限られていました。そして、物理的に近い場所にいるからこそ、コミュニケーション不足を補おうという気持ちになれないという課題を抱えていたのです。
また、約2,500人の社員のうち、デスクワーカーは4割しかいないという事実がわかり、会社にいない事が多い営業部門を対象に、オフィス面積の削減ができないかと考えていたのです。そこで、ただ単に省スペースのためだけではなく、プロジェクト単位で必要な人間がチームを組み、対応していくために「フリーアドレス制度」を導入しました。
・導入後の効果
同社の品川本社では、現在約2,500人の社員が働いていますが、そのうち60%はデスクを持たず、自分の好きな場所で働いています。フリーアドレス制度によって、上下関係や部署の壁を越えたコミュニケーションが自然に促されるようになりました。
伝える内容に合わせて伝達手段を選び、さらに移動する必要もないため、より手軽に、頻繁にコミュニケーションをとれるようになったのです。『組織図の線』がなくなり、プロジェクト単位で必要な人間がチームを組んで対応していくため、組織内コミュニケーションの活性化につながりました。
導入するにあたり同社では、伝達手段として「Microsoft Lync」というツールを活用し、いつでも誰とでもコンタクトがとれる仕組みを整えています。フリーアドレス制度を導入する際には、コミュニケーションツールの活用が必須となります。
「Microsoft Lync」とは、チャットやビデオ会議、インスタントメッセージなどのコミュニケーションツールを統合したものです。ヘッドセットを使って電話をかけたり、複数人でミーティングを行ったりすることもできます。
2-2-3.フリーアドレス制度はこんな人、組織にオススメ
フリーアドレス制度は、こんな悩みを抱えている人や組織にオススメです。
- 上下関係や部署を越えたコミュニケーションを円滑にしたい人や組織
- プロジェクト単位で人が自由に集まれるようにしたい人や組織
- より手軽に、頻繁にコミュニケーションをとりたい人や組織
フリーアドレス制度は、組織内全体のコミュニケーションを活性化します。これらの悩みを抱えている方は導入してみてはいかがでしょうか。
2-3.Skype for Businessの活用事例と効果(東京地下鉄株式会社※東京メトロ)
2-3-1.Skype for Businessとは
インスタントメッセージやビデオ会議など、あらゆるコミュニケーションツールを統合し、相手のプレゼンス(在席状況)に応じた情報伝達を可能にするユニファイドコミュニケーションプラットフォームです。
2-3-2.東京地下鉄株式会社のSkype for Business活用事例
・導入前の課題と目的
東京地下株式会社では、事業の特性上、拠点が複数広範囲に分散するため、効率的なコミュニケーションをとることに課題を抱えていました。駅、車両や線路のメンテナンスなどを行う技術系の拠点などが300以上、事務職から技術職まで、ワークスタイルの異なる約870名の従業員が働きます。
そんな中、電話、メールだけではカバーしきれないという現実に直面していたのです。そこで、多様なコミュニケーションニーズを満たすため、2007年にコミュニケーションツールとしてSkype for Businessを導入しました。※2007年当時は、Microsoft「Office Communications Server 2007」
・導入後の効果
事務系の社員を中心にSkype for Businessを業務に利用した結果、電話やメールほどの手間をかけずに簡易的なコミュニケーションが取れるようになりました。不在時の伝言メモなどには、インスタントメッセージを積極的に活用。事業の特性上、拠点が複数広範囲に分散する同社において、効率的なコミュニケーションを実現するツールとして重要な役割を担うようになりました。
ユーザーのPC利用状況を基に、「連絡可能」「退席中」など現在のプレゼンス(在席状況)が自動表示されるため、相手の状況にあわせて適切なツールを選択することで、効率的なコミュニケーションを行うことができます。別のフロアや離れたオフィスにいる相手の在席状況が一目でわかるため、対面でのコミュニケーションが必要な時に、『今すぐ相談しに行こう』『不在なのであとにしよう』といった判断がつくようになったからです。
インスタントメッセージやビデオ会議など複数のコミュニケーション機能も備えており、相手の状況にあわせて適切なツールを選択することで、効率的なコミュニケーションを行うことができます。
つまり、コミュニケーションを取りたい相手の状態や会話の目的に応じて、円滑なコミュニケーションを行えるほか、ツールの統合により管理の工数を低減できるようになったのです。
2-3-3.Skype for Businessはこんな人、組織にオススメ
Skype for Businessは、こんな悩みを抱えている人や組織にオススメです。
- 離れた場所にいる相手の状態に応じたコミュニケーションをとりたい人や組織
- 拠点がさまざまにある状況で円滑なコミュニケーションをとりたい人や組織
- シフト制などワークスタイルが異なる中で働く人や組織
Skype for Business制度は、場所を越え、状況にあわせた、円滑でより簡易的なコミュニケーションを実現します。これらの悩みを抱えている方は導入してみてはいかがでしょうか。
2-4.サンクスカードの活用事例と効果(株式会社武蔵野)
2-4-1.サンクスカードとは
「感謝」の気持ちをカードに乗せて「見える化」するための社内コミュニケーションツールの1つです。
例えば「〇〇をやってくれてありがとう」や「〇〇を頑張ったね」と、何か少しでもいいことがあったら、感謝や褒める言葉を名刺サイズのカードに手書きで書いて渡します。
2-4-2.株式会社武蔵野のサンクスカード活用事例と効果
・導入前の課題と目的
株式会社武蔵野の社長である小山昇氏は、自分が考えていることがどうしても従業員に伝わらない、口で言うだけでは通じないという課題を抱えていました。「褒めるときには、具体的に何が良かったかを褒めていく」という小山氏が大事にする考えを浸透させるために、サンクスカードを導入しました。「褒める」をルール化し、見える化したのです。
また、他人から親切を受けると、「ありがとう」ではなく「すみません」という社員の風潮に違和感を抱いていたこともあり、「ありがとう」の文化をつくれば、「すみません」よりコミュニケーションも円滑になるのではないかという目的もありました。
・導入後の効果
サンクスカードが増加するにともない、社内のコミュニケーションが円滑になり、雰囲気が明るくなりました。「ありがとう」と言えたり、言われたりすることで一緒に働く人を常に気にかけるようになり、親近感が芽生え、信頼関係が築け、より積極的にコミュニケーションを取れるようになったのです。
比例するように社員のモチベーションは向上し、社員の満足度が上がり、定着率も上がるという効果を得ました。そして、お客様満足度も上がり、業績も大きく向上したのです。
社長である小山氏の書いたサンクスカードが社員の子どもの目に止まり、「お父さん、すごいね」と言われたことで、一層業務に身を入れるようになり、大きな成果を出したそうです。それまでは各種表彰にも縁がなく、もちろん賞与評価もパッとしないような社員が目に見えて明るくなり、モチベーションの向上につながりました。
2-4-3.サンクスカードはこんな人、組織にオススメ
サンクスカードは、こんな悩みを抱えている人や組織にオススメです。
- 社内コミュニケーションを円滑にし、人間関係をより良くしたい人や組織
- 親近感を覚えて、信頼関係を築きたい人や組織
- 社員のモチベーションを上げたい人や組織
サンクスカードは、社内の雰囲気や人間関係をより良くし、信頼関係を構築するのにも役立ちます。これらの悩みを抱えている方は導入してみてはいかがでしょうか。
2-5.飲みニケーションの活用事例と効果(株式会社日立ソリューションズ)
2-5-1.飲みニケーションとは
飲みニケーション(のみニケーション)とは、社会で行われている人間同士でのコミュニケーションの形式の一つです。飲みニケーションは、会社や大学などといった場において、集っている人間が互いに距離を置いていたり、打ち解けることができていない場合には、共に居酒屋や飲み屋などといった場に出向いて酒を飲むことで、酔った勢いで互いが馴れ合ったり親密な会話ができるようになるということを目的として行われます。
2-5-2.飲みニケーション活用事例と効果
・導入前の課題と目的
2004年度に創業以来初めての赤字に陥った際に原因を分析した結果、社員の満足度が、他社に比べて低いという課題を抱えていました。精神的な問題を抱える社員が増え、危機感を持った同社が、2007年に社内の風通しや意思疎通をよくするために、飲食代の全額を会社が負担する形で、会社公認の飲みニケーション制度を導入しました。
・導入後の効果
単なる部署内の飲みニケーションではなく、役職が違う社員同士の飲み会を制度化し、一人3,000円の費用を会社が負担しています。直接の上司よりさらに上級の管理職や他部署との懇談会のため、同社では『段々飛び懇親会』と呼ばれています。
直属の上司とは違う角度から仕事の助言を受けたり、私生活の話題も気軽に話せるようになったため、精神的不調による休業者は06年度から11年度までに3割近く減少。退職率も4%台から1%台になる効果がありました。
他にも、違う課の課長同士が交流する会、テーマ別に生産性の向上や新製品のアイデアを話し合う会など、年間3,000回もの『飲みニケーション』が行われています。年間予算は約6千万円、約1万人の社員が年に1回は利用しています。
制度として導入することで、社内の風通しがよくなったり、意思の疎通がしやすくなったりと、より広いコミュニケーションを維持できるようになりました。
2-5-3.飲みニケーションはこんな人、組織にオススメ
飲みニケーションは、こんな悩みを抱えている人や組織にオススメです。
- 社内の風通しや意思の疎通をより良くしたい人や組織
- 社員の満足度を上げたい人や組織
- より広いコミュニケーションを取りたい人や組織
飲みニケーションは、社内の風通しをよくし、社員の満足度を上げるのに役立ちます。これらの悩みを抱えている方は導入してみてはいかがでしょうか。
3.ツールや仕組みを導入することが活性化への第一歩!
最後に、これから社内コミュニケーションを活性化していきたいという方にお伝えするのは、ツールや仕組みを導入することが、活性化への第一歩になるということです。
チャットワークを使うと、横のコミュニケーションが円滑になります。サンクスカードを使うと、信頼関係が構築されコミュニケーションが円滑になります。
チャットワーク、サンクスカード、飲みニケーションなどを導入した結果、社内コミュニケーションが活性化され、仕事の業績が上がり、働く人の満足度が上がっています。放っておいてもコミュニケーションは活性化されません。コミュニケーションをとるためのツールや仕組みを導入することが、活性化への第一歩なのです。
注:ご紹介したツールや仕組みは、どの業界、どの状況でも使えるわけではないということに、ご注意ください。
4.まとめ
あなたにとって、使える事例は見つかりましたか?社内コミュニケーションを活性化させるメリットは、ただ社員の業務がやりやすくなるだけではありません。社内の雰囲気が明るくなったり、社員が仕事を好きになってくれたりと、さまざまな副次的メリットが期待できます。これは会社を成長させるうえで、重要な要素であることは言うまでもありません。
そして、社内コミュニケーションを活性化させるためには、使っているツールや仕組みづくりがひとつの手段になりえるということがわかりました。課題が明確になった今、始めるのは簡単です。ご紹介した一つひとつは、すぐにでも始められるものです。ぜひ今回の事例を参考に、実践してみてください。
※個人レベルのコミュニケーションに関して詳しく学びたい方は、以下の記事もオススメです。
参考:
- チャットワークはフリーエージェント化するための必須ツール
http://www.chatwork.com/ja/case/kandamasanori.html - フリーアドレス制が変えたワークスタイル
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1205/15/news005.html