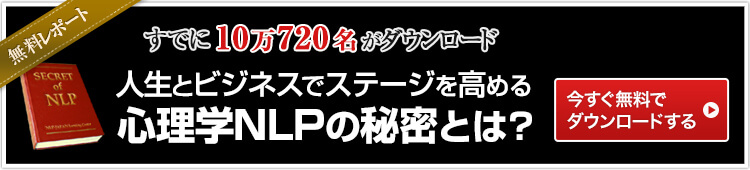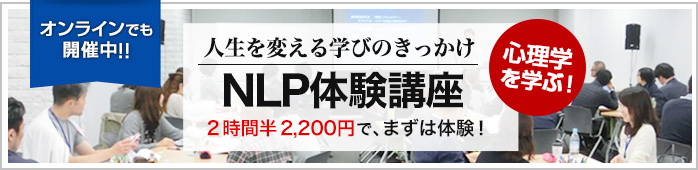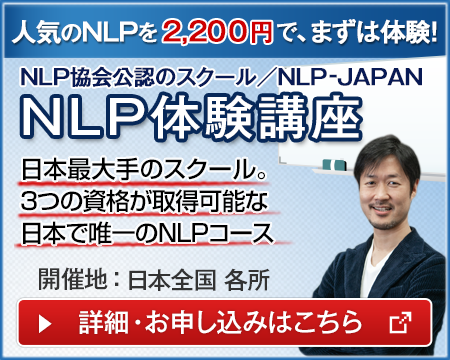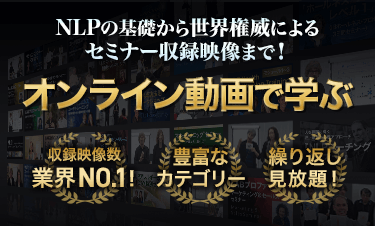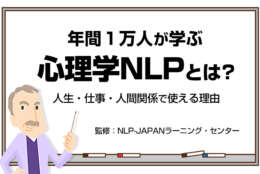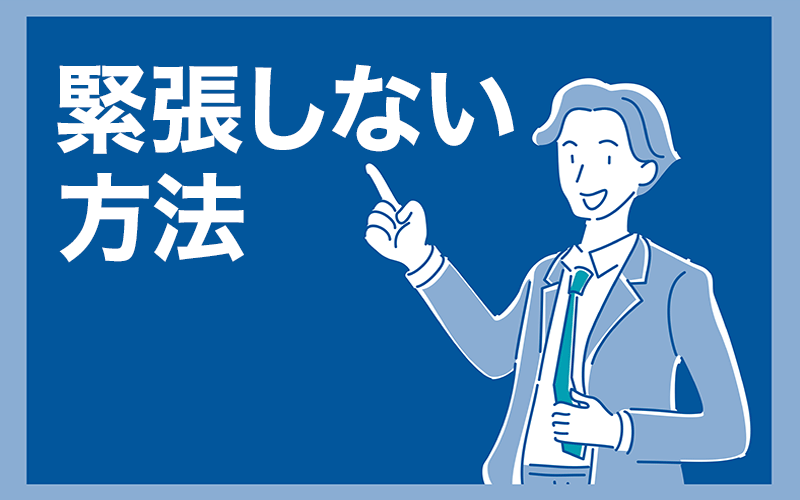
これまでの人生の中で、
緊張を上手くコントロールできず
失敗したり思い通りにいかなかった経験が
一度はあるのではないでしょうか?
もし「緊張しない方法」があるとしたら、
喉から手が出るほど知りたいという方も
いると思います。
また、
「緊張しない方法」をネットで検索したことや
本で読んだことを実践しても、
いまいちしっくりこなかったり
あまり変化がなかったりと、
そう簡単には上手くいかないことがほとんどです。
なぜ、世の中に溢れている
「緊張しない方法」を試しても、
緊張をなくすことができないのでしょうか。
それはあなたのセルフイメージが
大きく影響していると言われています。
本記事では「緊張しない方法」に加えて、
セルフイメージを向上させ、
さらに緊張の根本にある
過去の体験を克服していく方法を
実践心理学NLPを用いながらご紹介していきます。
著者:安藤 梨友(あんどう りとも) | |
男子新体操を4歳から22歳まで続け、現役中に全国大会で12回優勝した経験をもつ。 スポーツを通して、多くの一流の選手とそうでない選手に出会い、一流の選手とは結果を残すだけでなく、人柄や生き方が尊敬される存在だということに気づいた。 スポーツと人間心理を知ることで得た、実践的な学びを広めようと執筆に臨む。 | |
目次
1.「緊張しない方法」3選のご紹介
人生において緊張する場面というものは無数に存在していると思います。
- 初の取引先への商談やプレゼン
- 大口案件のプレゼン
- 大勢の前でのスピーチ
- 学校の受験や面接試験
- スポーツの試合やコンクールの本番など
ここに挙げた例に限らず、私たちはこれまでの人生で、度合いや程度の違いこそあれど、緊張した経験がある方がほとんどだと思います。
この章では、様々な場面で活用できる、「緊張しない方法」を厳選して3つご紹介していきます。
1-1.表情や姿勢を変える

「表情や姿勢を変える」
単純に聞こえるかもしれませんが、この手法は強力です。
なぜなら、この手法は脳の仕組みを逆手に取って、脳をうまく騙すことで緊張をほぐす、ということを狙いとしているからです。
その脳の仕組みとは、私たちは無意識のうちに、心と身体の状態が一致するようにできている、というもの。
そこで試しに、「落ち込み、悲しんでいる人」をイメージしてみてください。
多くの場合、目線は下を向き、身体はだるく重そうな感じがして、今にもため息が聞こえてきそうな姿勢をしていることでしょう。
逆に、「喜びに満ちて、活気に溢れている人」をイメージした場合、上記のような人物像が浮かぶことはないはずです。
そういう人はむしろ、目線は上で、立ち振舞いは軽やか。「よし!」という元気な声も聞こえてきそうな感じがしますよね。
つまり、目線は下を向き、身体はだるく重そうな感じがして、今にもため息が聞こえてきそうな姿勢をしている人は、決して「喜びに満ちて、活気に溢れている人」ではないと言えそうです。
こんな風に私たちは、心の状態と体の状態が、二つでセットになるような仕組みがはたらいている、と考えられているわけです。
このメカニズムを逆手に取れば、「体の状態を変えれば自ずと心の状態も変わる」ということになります。
僭越ながら私の経験でお伝えしますと、試合の前に緊張している時こそ、顔全体を使って満面の笑顔を意図的に作ってから、本番の会場まで胸を張って堂々と歩くようにしていました。
そうした習慣をつくり、実践することで脳を騙し、緊張している状態から自信満々で余裕がある状態へ、簡単に切り替えることが可能になっていきました。
シンプルな手法ではありますが、自分の意志で緊張をほぐすことができるので、繰り返し実践すれば非常に強力な手法だといえます。
1-2.「緊張」を身体の中から吹き飛ばす

二つ目は、「緊張」を身体の中から吹き飛ばすという方法です。
この手法も実践すれば、あなたも気づくことになるかと思いますが、その効果は抜群です。
かんたんに例えるのならば、この手法の原理は「痛いの痛いの飛んでけー」です。
特に幼少期や子育ての際によく耳にする言葉だと思いますが、原理は非常によく似ていて、実践心理学NLPでは「サブモダリティ」と呼ばれています。
「NLPとは?」
Neuro Linguistic Programing(神経言語プログラミング)の略称で、別名「脳と心の取扱説明書」とも呼ばれる最新の心理学。
元はカウンセリング手法として、心に深い傷やトラウマ(PTSD)を負った兵士たちの治療のために用いられ、際立って効果を発揮したことから注目されるようになってきました。
現在では、心理学NLPの高い効果を得るために、世界のトップビジネスシーンやスポーツの世界などでも幅広く活用されており、日本ではすでに2万人を超える方が学んでいます。
カウンセリングやセラピーの現場では、自身の感情(幸福感や不安、緊張など)を抽象的なイメージに例えて、クライアントの状態を改善に導いていく手法があります。
例えば、イライラしている人に、その「イライラ」を感じる場所や色、形などを聞いてみると、
「お腹のあたりに黒くてトゲトゲしたものがあります。」と答えました。
またある人が幸福感や愛情を感じたときに、それを感じる場所や色、形などを聞いてみると、
「左胸のあたりにぼんやりとオレンジ色に光っていて、例えるなら小さい太陽のような、かすかにあたたかいものがあります。」と答えました。
このように自身の感情や状態を身体の中にイメージをして、何かモノに例えてみることがあります。
話をもとに戻すと、
「痛いの痛いの飛んでけー」と言うだけで、
子どもが怪我をして大泣きしていた様子が落ち着いたり、上手くいけば泣き止んでしまうケースもあると思います。
これって不思議だと思いませんか?
恐らく、「痛いの痛いの飛んでけー」と言われた子どもの怪我が一瞬で完治することもないですし、痛みが急激に軽減されることがないことも想像がつくかと思います。
しかし、子どもの様子は落ち着き、泣き止むのです。
これは子どもが感じている「痛み」をイメージの中だけでも身体から切り離し、手を振りながら「痛み」を遠くに飛ばす動作を同時に行うことで、実際に「痛み」が飛んでいったような感覚になるからです。
これと同じことが、「緊張」でも可能であれば試してみたいと思いませんか?
興味のある方はぜひ、読みながらできるデモンストレーションとして、このまま読み進めてみてください。
それでは、実際にご自身が緊張している時の身体の状態をイメージしてみてください。
- 硬直して上手く身体が動かない
- 頭の中が真っ白になる
- 心臓の音が大きく聞こえる
など、緊張している状態というのは他にも様々あると思いますが、主な例としては上記のようなものが挙げられます。
そして、その「緊張」は身体のどの部分で感じ、どんな色や形、大きさをしているでしょうか?
例として私は、左胸の辺りに、拳一つ分くらいの黒くどろっとした球体をイメージすることができます。
そしてその黒い球体を、身体の外に出していくイメージをします。
一度で出し切れない場合は、何度も繰り返し行うことをおすすめします。
また、余談ですが私は身体全体をフラスコのようなものであるとイメージし、入り口の部分から黒い球体を押し出していくイメージをして、身体から「緊張」を取り除いていました。
すると、不思議なことに呼吸は整い、頭もクリアになって身体も落ち着いた状態にすることができます。
これが二つ目の「緊張」を身体の中から吹き飛ばすという方法です。
是非、実践してみてはいかがでしょうか?
1-3.本番を具体的にイメージする

三つ目は、本番を具体的にイメージするという方法です。
「練習は本番のように。本番は練習のように。」
という言葉がありますが、練習の時点でいかに本番と同じ状況を作れるのか、ということが非常に重要なポイントになってきます。
そのため、「想像力」がカギとなってくるわけですが、むやみやたらとイメージするだけでは、中々うまくいかないのも事実です。
そこで、心理学に基づいた、大切なコツをお伝えします。
それは、「環境面」と「メンタル面」の2つの視点でイメージを作るということです。
「環境面」というのは、いわゆる五感を通して得られる情報のことです。
例えば、本番の会場やホールに実際に足を運ぶことで本番と同じ景色や感覚を一度体験することができ、練習の際に本番をイメージすることが比較的簡単になります。
しかし、本番の会場に一度も行ったことがないまま、当日を迎えるケースも少なくないと思います。
その場合は、インターネットで会場の風景を調べたり、自分の頭の中で様々なパターンを想像しておくことで、より一層、練習の環境と本番の環境の差異を少なくすることができます。
次に「メンタル面」についてです。
こちらは1ー1で説明した部分と少し重なる点がありますが、要は精神的な状態も本番と同じ状況を鮮明にイメージする必要があります。
では、どうやって本番と同じ(近い)状態を作り出すのか。
それは姿勢や行動を変えるのです。
例として、私が実際に行っていた方法をご紹介します。
私は、練習で失敗をしてしまった場合、部室に行って無理やり泣く(涙を流す)ようにしていました。
これは、この一度のミスが勝敗を分け、本番だったら優勝を逃していたのだと鮮明に想像することで涙を流しミスしたことの重大さを再認識することができ、緊張感が生まれます。
実際に練習の中で本番と同じ精神状態を作り出すことは、非常に難しいことだと思います。
しかし、あえて泣くという行動をすることで練習と本番を限りなく近づけて、最大限の緊張感を保つことができていたのです。
このように、「環境面」と「メンタル面」のどちらにおいても練習を限りなく本番のイメージと近づけていくことで、本番の緊張すらも練習から鮮明に想像することができます。
さて、3つ手法をお伝えしてきましたが、これらのようなテクニックは誤解を恐れずに言うと、「付け焼き刃」的なもの。
長い目で緊張そのものを本格的に克服していきたい、と思ったら、次にご紹介する「セルフイメージの改善・向上」が必須といえます。
まず、そもそも私たちはなぜ緊張してしまうのか?
その原因やからくりを、実践心理学NLPを交えながらお伝えしていきます。
2.緊張を引き起こすセルフイメージとは?
そもそも、どうして人は緊張してしまうのか?
驚くべきことに、自身で作り上げたセルフイメージが「緊張」にも大きく影響していると言われています。
この章では緊張を引き起こしているセルフイメージとはどういったものなのか、詳しくご紹介していきます。
2-1.セルフイメージ

まずセルフイメージとは、「自分自身に対して抱いているイメージ」のことです。
例としては、
- 自分は〇〇な性格だ
- 自分の長所は□□で、短所は△△だ
- 自分は周囲から♢♢と思われている
などといったものが挙げられます。
このセルフイメージは、過去に起きた全ての出来事や環境などが要素となって作り上げられていきます。
例えば、
学校の運動会で常に1位を勝ち取っていたA君は
「僕は運動神経が良くて、スポーツが得意だ。」
といったセルフイメージが作られます。
一方で、
運動会でいつもビリだったB君は
「僕は運動神経が悪くて、スポーツが苦手だ。」
というセルフイメージが作られることは容易に想像できるでしょう。
A君とB君、それぞれどちらが良い悪いではないですが、過去の経験によって作り上げられたセルフイメージは、その先の人生において大きな影響を及ぼしていくことになります。
2-2.過去の失敗体験やマイナスな出来事

セルフイメージは、過去に起きた出来事によって作り上げられるとお伝えしましたが、「緊張してしまう」というのも自身の過去を振り返ってみると根本となる原因が浮かび上がってくるかもしれません。
なぜなら、多くの人が緊張するシチュエーションの裏側には
- 大勢の前で失敗したくない
- 恥ずかしい思いをしたくない
などといった心情があると思います。
これらは裏を返せば、大勢の前で失敗した経験があったり、それによって恥ずかしい思いをしたことがあるということです。
一度も失敗をしたことがない赤ちゃんは、失敗を恐れて緊張をするということはないですよね。
人は無意識のうちに過去の失敗体験の記憶から、現在の自身の行動に制限をかけてしまったり、失敗を恐れて挑戦すること自体を辞めてしまうことがあります。
いわば、それが「緊張」を引き起こしているセルフイメージということです。
私にとっての最初の失敗体験は、
「幼稚園の運動会で行われた跳び箱発表会で
大勢の人の前で大失敗をした」
というものでした。
思い返してみると、この体験があってから、大勢の前で何かを発表することに対して「緊張する」という感情が生まれたと思います。
また、本題とは少しずれてしまうのですが、この跳び箱発表会で失敗する前は、私の頭の中に「緊張する」という概念がなかったにも関わらず、大勢の前で大失敗してしまうということは、
緊張=悪いこと
緊張しない=良いこと
とは、一概には言い切れないと思います。
恐らく、緊張したら演技が悪くなるわけではなく、緊張しなかったからと言って良い演技ができるわけでもないのでしょう。ですが、過去の失敗と結びついているような緊張は、克服していきたいものです。
もし、過去の自分の失敗体験が、緊張を生み出しているかもしれないと思われた方は、セルフイメージを高めたり、過去のマイナスイメージが現在のご自身に影響しないようにしていくことが、緊張やあがり症の克服に必要不可欠となってきます。
そして、過去の失敗体験を癒やすためにはセラピーを受けたり、Life&Mindの運営元のNLP-JAPANラーニング・センターでマイナスイメージを改善するようなアプローチを学ぶことができます。
本記事の後半部分で、NLPについて少し触れているのでご興味がある方は是非読み進めていってください。
3.セルフイメージを高めるには?
高いセルフイメージをもつことができれば、大事な場面で緊張することがなくなったり、緊張したとしてもすぐに落ち着いた状態に切り替えることもできるようになります。
この章では、そんなセルフイメージを高める方法をご紹介します。
3-1.小さな成功体験を積み重ねる

セルフイメージを高めるために、最も効果的かつ基本であり、不可欠な方法です。
- ずっと気になっていたご飯屋さんに行ってみる。
- 学生時代の友人に、再会の連絡をしてみる。
- 両親やお世話になっている方にお礼を伝えてみる。
など、これらは一例ではありますが、本当に小さいことで良いので100個の目標を立てて達成してみましょう。
具体的な方法としては、ノートに箇条書きで100個のリストを作成して、達成することができた目標には赤いペンで線を引いて、『達成!』と書いていきます。
- ◯日までに□をする。
- △日までに◇を行う。 達成!
こうすることで、10個達成、20個達成、30個達成、、、と目標をどんどん達成していくことで、自分のセルフイメージが高まっていくことを実感できるでしょう。
また、100個を達成した後もまた新たな目標を立てて、同じように達成していくことで継続的にセルフイメージ向上を促進することができます。
是非、試してみてくださいね。
さて、これまでいくつかの方法をご紹介してきており、セルフイメージを高めたり、過去の失敗体験などが頭をよぎることが緊張に大きく影響するということでしたが、それらを解決するアプローチを実践心理学NLPでは学ぶことができます。
もし、NLPにご興味があれば、95,000人以上の方が既に読んでいる無料レポートをダウンロードして読んでみていただくか、NLPの体験講座もたくさんの方が参加されているので、ご興味ある方はご参加してみてください。
95,000人以上の方がダウンロードされている無料レポートはこちらから。
↓
人生とビジネスでステージを高める心理学NLPの秘密
心理学NLPの体験講座はこちらから。
↓
NLP体験講座(東京・名古屋・大阪・福岡・オンラインで開催中)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事では、緊張しない方法を厳選して、この3つをご紹介しました。
- 姿勢を変える
- 「緊張」を身体の中から吹き飛ばす(サブモダリティ)
- 本番を具体的にイメージする
また、緊張を引き起こしているセルフイメージをどのように向上させていくのかという具体的な方法を、ご紹介しました。
「小さな成功体験を積み重ねる」
ぜひ試してみてください。
そうすることで、「緊張しない方法」に加えて、セルフイメージを向上させ、さらに緊張の根本にある過去の体験を克服していくことができるでしょう。