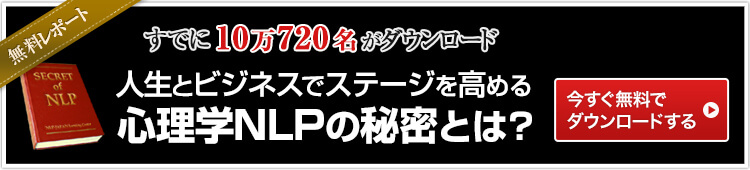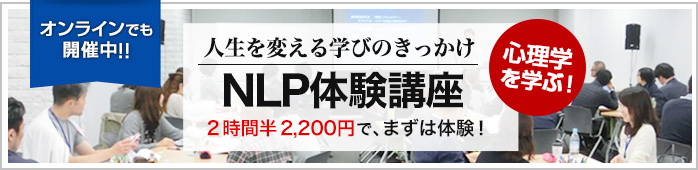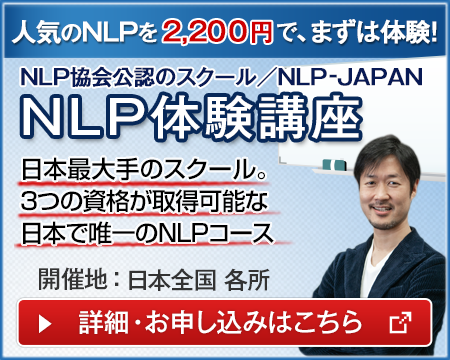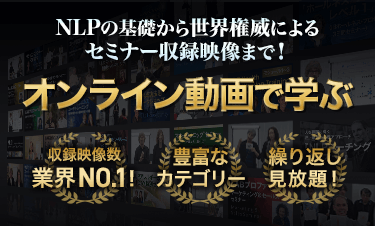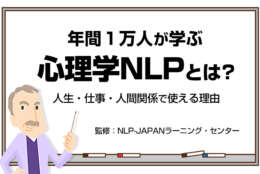「怒りをコントロールする方法」は、
世の中にたくさんありますが、
気づいたら既に手遅れだったり、
小手先のものをいくら試したところで、
くり返す失敗は変わらなかったのではないでしょうか。
本来、怒りという感情は、
自分を守るために発せられるので、
とてもパワフルなのです。
ここでは、人間心理や身体へのアプローチを含め、
湧き上がる怒りの応急処置法9個と、
引きずってしまう怒りへの対処法6個、
合計15の方法をご紹介していきます。
気になるものから早速取り組んでみてください。
目次
1.言葉を飲み込む

怒りをコントロールする方法の1つ目です。
暴言を吐く代わりに、言葉を飲み込みましょう。
衝動的な怒りのコントロールは、とても難しいものです。
「カッとなった」ときに動きを止めることは難しいので、代わりの行動を作っておく事が効果的です。
「カッとなったら飲み込む(代わりの行動を取る)」という繰り返しで、徐々に怒りの爆発を止められるようになっていきます。
そして、応急処置で飲み込んだ怒りは、12~15の方法で解消していってください。
2.環境を変えて落ち着く(タイムアウト)
タイムアウトとは、場所を変えたり、時間を変えたりして、自分の怒りの感情を落ち着かせることです。
その人との距離や話す位置を変えたりして、怒りの感情を切り離します。
3.呼吸を深く、ゆっくり行う
文字通り呼吸を変えて、感情を静めてください。
多くの場合、怒りの感情が出てくるときは、呼吸が荒れています。または止まっている状態です。
深い、静かな呼吸を意識してとり、怒りをコントロールしていきます。
4.数字を数える
6秒間を過ぎれば、怒りそのものの感情はなくなると言われています。
ですから6からでも1からでもいいので、数を無言で数えながら、怒りをコントロールしてください。
6秒ルールを意識しましょう|けんぽれん[健康保険組合連合会]
5.目を上にあげる
脳と心の取扱説明書と呼ばれる心理学NLP(神経言語プログラミング)のアイパターンと呼ばれる考え方を活用して、怒りをコントロールすることができます。
NLPのアイパターンとは、目の動きと脳の情報処理の関係性をパターン化したものです。
怒りだけでなく、感情を脳で処理している時、私たちの視線は下に向いています。怒りの感情に気づき始めたら、すぐに目を上のほうに向け、感情を司る脳へのアクセスを断ち切ってください。
不安やパニックといった状態でもこのことは効果的です。
6.全く関係ないものに視点を移す(ツールを変える)

ここでいうツールとは、愛着のある写真やグッズのことです。
写真で言えば、大切な家族の写真とか、ペットの写真などです。グッズは、大切な人からもらったプレゼントやその他のあなた自身が大切にしているモノです。
怒りが出てきそうになったら、携帯やパソコンの壁紙などの写真を見たり、グッズに目を向けて、そのツールに関連している感情を思い出しながら、怒りの感情を緩和させていきます。
7.ジェームズ=ランゲ説を活用する(筋肉の状態を変える)
アメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズと、オランダの心理学者カール・ランゲが提唱した、『ジェームズ=ランゲ説』という考え方があります。
簡単に意訳してお伝えすると、感情は体で先に知覚して、その後で心で感じるという考え方です。
| 例)悲しくて涙が出る状態 |
|---|
| 「泣く→悲しい」この順番で、私たちは感情を処理している |
「人は悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しくなるのだ」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、まさにこのことです。
動物の本能的な反応を思い浮かべるとわかってくると思います。
敵が現れたストレス状態の時には、逃げる、または戦うといった状態で、筋肉が緊張状態にあります。これは刺激に対する身体反応の一種です。
表情の筋肉でも感情と関係があります。
| 感情 | 表情の筋肉 |
|---|---|
| 喜び | 目の周辺の筋肉が収縮し、口角が上がる |
| 怒り | 眉間にしわがより、歯を食いしばるといった反応をする |
| 哀しみ | 顔の中心に向かって筋肉が収縮する |
つまり、筋肉の状態と感情には相互に関係があり、感情を変えたければ、表情や姿勢といった筋肉の状態を変えていけばいいわけです。
表情から変えてもいいですし、姿勢を変えて怒りをコントロールしてもかまいません。表情や姿勢を変えて怒りをコントロールしてください。
※もちろん他の説はありますが、ココでは、怒りのコントロール法の選択肢を増やすことを目的にご紹介しています。
8.「視点」を変える
ここでご紹介する「視点」というのは、先にお伝えした心理学NLP(神経言語プログラミング)の中の「知覚位置」という考え方を活用します。
知覚位置とは、下記3つで物事をとらえると、その出来事や人に対する意味や解釈が異なって認識できるというものです。
- 「自分の位置」
- 「相手の位置」
- 「第三者の位置」
怒りを感じている時、最も認識しやすいのが「自分の位置」です。人との関係で怒りを感じている時であれば、まさに今自分の目でみて、自分の耳で聞いて、感じることができている情報です。
そこから見ているという自覚もなく認識できている世界ですね。
これを第三者の位置でとらえなおすと、怒りの感情が薄らいだり、慣れてくると感じることすらできなくなります。
この第三者の位置や視点とは、例えば、壁にとまっているハエの視点とか、天井の蛍光灯からみた自分と相手の姿、といった視点です。
もっと極端に視点を高めるならGoogleマップの「写真」を想像するとわかりやすいでしょう。
グンと視点を大空にもっていって、自分が存在している地上を見下ろすようにすると、怒りの感情と自分自身の感情を容易に切り離すことができてきます。

9.伝え方を穏やかな表現に変える(アサーション)
アサーションというコミュニケーションのスキルがあります。
簡単にお伝えすると言いたいことを飲み込んだり、相手を責める表現を使ったりすることなく、自分も相手も理解し尊重したうえで、自分の意見を適切な言い方で伝えるコミュニケーションスキルです。
人に対して怒りの最中にいる時、良い人間関係、円滑なコミュニケーションを築くためにこのアサーションを活用すると効果的です。
アサーティブな表現とは、自分の気持ちを正直に伝え、かつ相手にも配慮した言い方です。効果的に活用するために以下のステップを参考にしてください。
① 自分の気持ちを考える
自分の正直な気持ちはどういうものなのかをしっかりと特定する。
② 相手の気持ちや立場を考える
自分の気持ちを一方的に伝えるのではなく、それを言われた相手がどのように感じるのか、と想像します。
③ 伝える言葉を考える
怒りを感じている時は、色んな場面があっても結局のところ「あなたは間違っている!」「あなたはヒドイ!」「あなたはわかっていない!」ということを伝えたがっています。
ここを「あなたは・・・」と言うメッセージでなく、「私」を主語にして言葉を作ります。
そして、建設的で肯定的な言葉をもちいます。
例えば、
- 「私は、○○練習が必要になってきます」
- 「○○してくれると私はやる気が出ます」
- 「私は○○で困っています。☆☆していただけないでしょうか」
という表現です。
少し練習が必要になってきますが、慣れてくると、自分の怒りを飲み込むことなく、かつ散らかすことなく、コントロールできるやり方です。
一方的でなく、建設的な意図が伝わるように伝えてください。
ここまでが、応急処置法でした。このまま続けて、怒りやイライラがなかなか解消しないときに効果的な、怒りのコントロール方をご紹介していきます。
もしも自分は怒りっぽい方なのか気になっているという方は、以下のチェックリスト付きの記事をご覧ください。
10.ツボ(百会)を刺激する

ツボの効果はすでにご存じだと思いますが、怒りを鎮める効果があるのは「百会(ひゃくえ)」です。
ここをゆっくり押して怒りを解消させてください。
百会は、左右の耳をむすぶ線と鼻からの延長線が交わるところにあります。
11.マッサージで身体を緩和させる
ここでは、心理療法の一つにあるSAT(サット)理論を基盤としたマッサージ、「スキンシップ法」をご紹介します。
- 二人で行います。怒りを緩和したい人が、自分の怒りを想起したとき、0~100%の数値でその怒りを数値化します。
- その怒りをイメージすると体のどこの部分がストレスを感じるかを特定します。(頭が重い、首が固くなる、おなかが痛いなど)
- その症状がどうしたら楽になるかを直感的にキャッチし、相手に伝え、相手の体をかりてどのようにマッサージ、指圧などをしたらいいか実際に施術します。
- 相手は言われたとおりにマッサージ、または指圧します。時間は1から2分を目安に楽になるまで相手は強さやテンポなど要求どおりに行います。
- スキンシップ(マッサージ・指圧)を終えたら、自分の体がどのように変化しているか、0~100%の数値で怒りを数値化します。
やればわかりますが、非常に効果的です。
※参考文献:SAT法を学ぶ, 宗像恒次監修, 金子書房
12.怒りの理由を考える
そもそもなんで怒りを覚えているのか、腹が立っているのかを考えてみます。
怒りの理由は、この3つによります。
- 期待どおりに行かなかった(想定していた前提が崩れた)
- 正しい/大切だと思っている価値観を否定された
- 体調不良だった(コンディションが悪かった)
まずは、この3つの理由に当てはめてみてください。
自然と何が目的なのか、何が予想と違っていたのか、期待と違っていたのか、どんな価値観が大事にされていないと思ったのかに気付けば、怒りが軽減され、新たな対応が浮かび、選択肢が見えてくると思います。
相手は「わかっているつもり」「知っているはず」といった、自分の前提や価値観をこの機会にぜひ相手と共有してください。
13.紙に書き出して、破る

これはとにかく怒りの感情を紙に書き出すやり方です。
運動をして、怒りのエネルギーを発散させることとポイントは同じです。
ひたすら書いて、書いて書き出して、自分の中に引きずっている怒りのエネルギーが放出するまで書きなぐってください。
そして、書き出したら、その場でもいいですし、一晩時間をおいても大丈夫です。冷静に読めるようになったら、書き出した紙を破ります。
ハサミで切っても、カッターで切り刻んでも大丈夫なので、スッキリして、馬鹿らしくなるまでやってください。
14.五感情報を変化させる
人は内側でイメージしたり、自分や誰かの声を聞いたり、体の中で怒りをはじめとする感情の形や温度や重さ軽さを感じています。
この内側で見たり聞いたり感じたりする、内的な五感情報を変化させることによって、怒りをコントロールすることができます。
想像力が必要になりますが、ここではこの五感情報を活用した3つのアプローチをご紹介します。どれか一つは取り組みやすいものがあると思いますので、その一つに慣れてきたら、他のアプローチも組み合わせながら試してみてください。
視覚情報を変える

リラックスした状態で「その怒りのことを考えたときに浮かぶ映像はどんな映像か」、と自分に問いかけてください。「怒りの対象を思い浮かべるのではなく、怒りのことを考えたときにポンと浮かぶ映像」というのがポイントです。
そこに浮かんでくる一枚の映像を特定します。
下記のような加工をしてみてください。
- 大きい⇒小さくする
- カラー⇒白黒にする
- 左側にある⇒右側に移す
- 自分との距離が近くにある⇒遠くに離す
抱いているその怒りの感情が薄くなるまで、編集したり加工していきます。
特に、次のような要素を参考にしてください。
- 色
- 明るさ
- 動き(静止画か動画か)
- 距離
- 位置
- 枠があるかないか
- 自分が写っているか、写っていないか
これらの要素を変化させていきます。
聴覚情報を変える

怒りの対象を想像したとき、その時に聞こえてくる音を特定します。
例えば、場所はどこか、どんなセリフか、その声は高いか低いか、その声は速いか遅いか、リズムはあるかなしか、といったことを特定していきます。
それが特定できたら映像と同様、下記のような加工をしてみてください。
- 自分の近くで聞こえる⇒遠くに離す
- 聞こえてくる場所が右側⇒左側に変える
- セリフのスピードが速い⇒遅くする
- 誰かの声であれば声質を変える
抱いているその怒りの感情が薄くなるまで、加工していきます。
具体的には、このような例も参考にしてください。
| 状態 | 加工・編集 |
|---|---|
| 頭の右上から聞こえてくる | 左足の小指に音の発信先を移す |
| 苦手な人の声で聞こえる | ミッキーマウスの声に加工する |
| セリフが明確に聞こえる | セリフを逆再生する |
上記3つ目、セリフの逆再生とは「なにやってんだ、君は」というセリフでしたら、「わみきだんてっやにな」と逆から音をきいてみる、ということです。
「うとがりあ」ときいてもピンときませんが、これは「ありがとう」の逆再生のセリフです。逆再生は、言葉が持つ意味をなくしていくのに効果的ですので、これらを使ってあなたの怒りを解消させてください。
慣れてくると、怒りどころか、笑えてきますので、そこまで出来るようになったら、怒りのコントロールは容易になります。
体感覚情報を変える

怒りを体のどこで感じているか探してみて、それを以下のように特定してみます。
例えばゴツゴツした岩のような形とか、鉄のような棒とか、三角すいのような形、といった具合に「形」で表してみます。
それが特定できたらこれまでと同様、下記のような加工をしてみてください。
もしも、その「形」に触れられるとしたら、、、
- 強度が硬い⇒フワフワに柔らかくする
- 肌触りがザラザラ⇒ツルツルにする
- 重い⇒軽くする
- 冷たい⇒ポカポカ温かくする
視覚情報、聴覚情報同様、怒りが軽減し、対処できるようになるまで取り組んでください。呼吸とともにその体感覚情報を体の外に出していくというイメージを使っても効果的です。
ここでご紹介しているのは、先に紹介したNLP(神経言語プログラミング)のサブモダリティと言われる概念が基盤となっています。より詳しく学びたい方は、以下の書籍や記事を参考にしてください。
※参考文献
- 成功心理学 プロが教えるNLP入門 芝 健太(著), 居山 真希子(著), 桶谷 和子(著),出版社:GENIUS PUBLISHING
- 神経言語プログラミング―頭脳(あたま)をつかえば自分も変わる リチャード・バンドラー(著),出版社:東京図書
- 感情、思考、思い込みに影響を与える『サブモダリティ』とは
15.成長の機会になる問いかけ

これは、怒りの感情を成長の機会としてとらえるための具体的なやり方です。
怒りは、「今のやり方では通用しない」「このやり方では理想に近づけない」「止めている何かがある」という、あなたを成長させるシグナルやメッセージとしてとらえます。
柔軟性があり、仕事がデキる人は、怒りを「他のやり方を求められている」「これではない、他の視点を必要している」といった意味で、成長や学びの機会にしています。
ぜひ、以下の問いかけを活用してください。
「自分の成長のために、この怒りは私に何を教えようとしているのか?」
「この怒りのエネルギーを、もっと価値あることに使うために自分にできることは何か?」
「もし、今日が人生最後の日なら、このことに時間を割くか。それとも他のどんなことに時間を使うか?」
ここまで、湧き上がる怒りの応急処置法9個と、引きずってしまう怒りへの対処法6個、合計15個の方法をご紹介しました。
これらの方法が、あなたの怒りをコントロールする助けとなることを願っています。
もし、さまざまな怒りのコントロール方法を試しても、どうにも収まらない…という方には、以下の記事がオススメです。